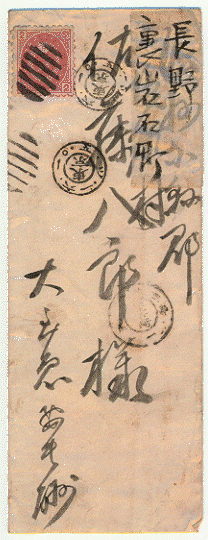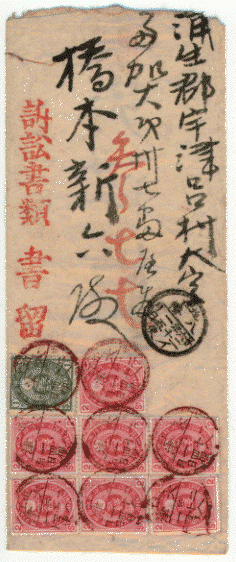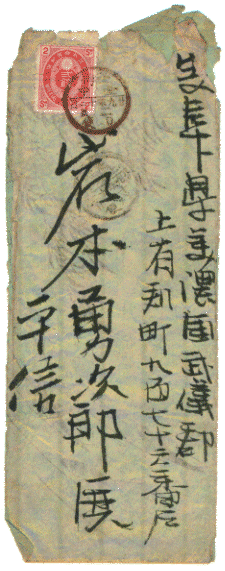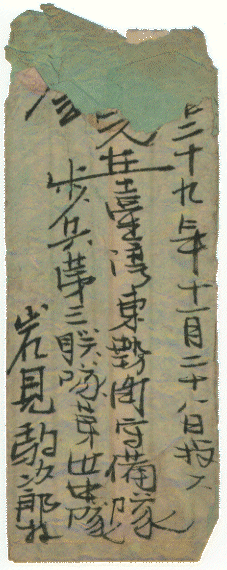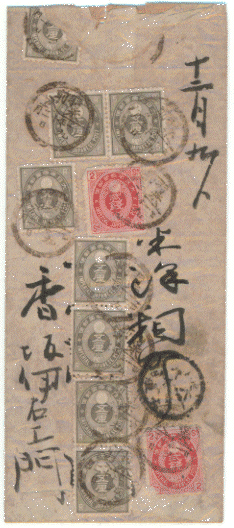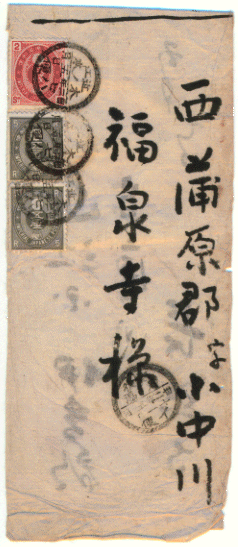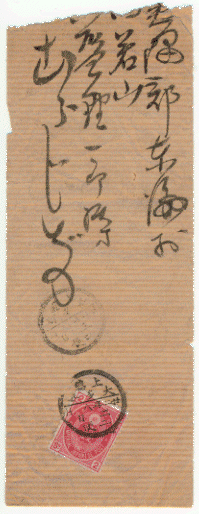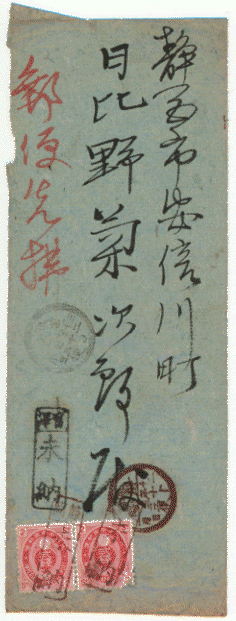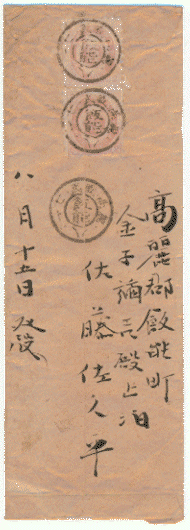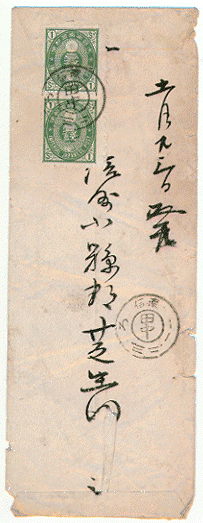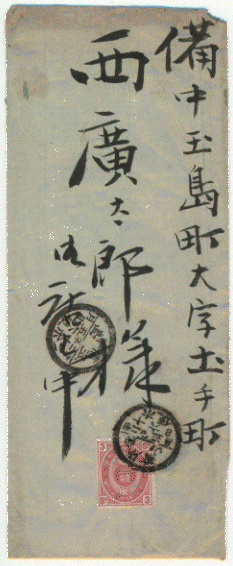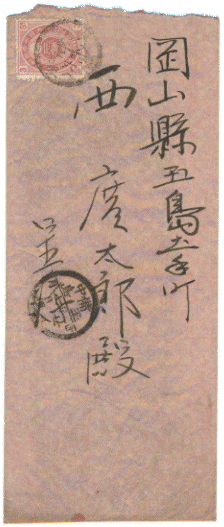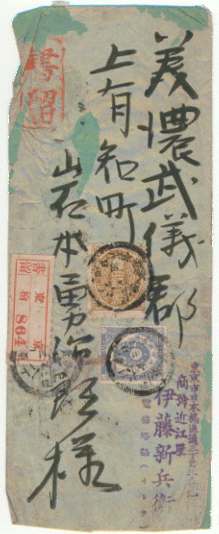|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
新小判切手と「赤二」の話や手紙あれこれ
明治4年3月1日に郵便制度が施行されましたが、郵便箱と呼ばれたポストは、江戸時代
の灯明台や火災防止の施設のようで、この箱に入れた手紙がどうして届くのか、何か箱に
仕掛けが有るのかと、郵便箱を覗き込む人もいたそうです。
発達した外国の切手製造機械を輸入し、切手の大量生産に取り組み、国内のあらゆる場所
に平等に均等に行き渡らせたことは、当時の人々に大きな驚きを与えたのです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
最初の明治4年3月発行の「手彫り」48文切手が394.088枚、「銭」となり、
「銭」と書かれた切手が改められ、明治9年5月発行の青灰色5厘の切手の発行数が
177.714.127枚、明治12年10月発行の赤褐色の一銭切手が102.014
.217枚、明治16年1月発行の紅色(ROSE CARMINE)二銭切手は、1.407.00
0.000枚が発行され、想像をはるかに超えた数量であり、今でも驚きそのものです。
発行した日数も5.844日、大正毛紙三銭切手の7.828日に次ぐ長さです。その紅
色二銭の切手は、俗に「赤二」と呼ばれた切手で、使用された手紙も夥しい数にのぼりま
す。ですから、「お宝」というにはあまりにも月並みです。駄物だと云って目もくれない
人も多いのです。目打ち(20ミリメートル内の穴の数)は、8から14×14まで47
種類以上。切手の刷り色は、紅色から淡紅色(ROSE)まで濃淡の差が著しく、これらの組
み合わせで切手は千差万別。これ以外に、書留、不足、消印、発進局印、受信局印、日付
印など、郵便のいろいろな事が分かるのです。